絶対音感保有者の音楽的音高認知過程
1997年度〜1998 年度 文部省科学研究費補助金 (基盤研究 C ) 研究成果報告書
(1999年3月)
目次
- 音楽的音高の特質
- これまでの研究
2.1 絶対音感の正確さ
2.2 絶対音高認知における音色と音域の効果
2.3 絶対音高認知における白鍵音と黒鍵音の差別化
2.4 絶対音感保有者の音程の知覚
2.5 絶対音感保有者の割合
- メロディの認知
3.1 実験1
3.2 実験2
3.3 実験3
- 結論
- References
絶対音感は、他の音高と比較することなく、単独に聞こえてきた音の音楽的音高名を即座に答えることができる能力である。この能力は3-6歳頃の音楽的訓練によって獲得されると考えられており、音楽と関連が深い能力とされている。日本では幼児期からの音楽教育が広く行われていることもあって、音楽経験者の中に絶対音感の能力を持つ者の割合が諸外国にくらべて高いと言われている。しかし絶対音感を持つ人々が音楽をどのように知覚・認知しているのかについての実証的研究は比較的少なく、まだ明らかになっていない点が多くある。本研究は、これらの問題を明らかにするために、絶対音感を持つ人々を被験者にして行った、音高・音程・メロディの認知に関する心理学的実験を中心とした研究である。従来、絶対音感は音楽家にとって有用な能力と考えられてきた。しかし音楽においては、メロディや和声を作っている音高の間の関係(相対音高)が重要なのであり、個々の音の音高名を言い当てる能力は音楽的には本質的なものではない。それどころか、絶対音感を持っていると、音楽的に重要である相対音高に関する課題遂行が困難になる可能性が考えられる。本研究では、従来目を向けられることがなかったこのような絶対音感の持つ問題点について、実証的な資料を提供しようとするものである。
1. 音楽的音高の特質と絶対音感
音のきこえの諸属性の中で音高は、人間の聴覚経験において重要な意味を持っている。話し言葉においては、音の高さの変化パターン (抑揚) は意味伝達の上で重要な役割りをになっている。たとえば音韻の点では同一の言葉も、抑揚が異なるとまったく違った意味になることがあるし、文の抑揚のパターンは、文字として表される言語的情報の他に、重要な意味的、あるいは情緒的情報を伝える。しかし言葉における以上に音の高さが本質的に重要な働きをしているのは音楽においてである。旋律や和声といった、音楽の基本的構成要素は、高さに関して音が秩序づけられることによって成立するものだからである。
物理的事象と心理経験との対応関係を明らかにしようとする心理物理学(psychophysics) では、音の高さは、音波の基本周波数という物理量に対応する心理経験であり、周波数が小さい値から大きい値に連続的に変化していくにつれ、我々は低い音から高い音への連続的な変化を知覚する。人間の聴覚系は、音の高さの違いに関してはきわめて敏感である。継起する2つの音の高さの違いを聞き取ることができる周波数差の最小値 (周波数弁別閾) は、個人差はあるが、普通の人でも0.2%程度であるとされている(Moore,1982)。この値は、耳の鋭い音楽家ではさらに小さく、0.1%以下になる。
このように人間は、音の高さの比較判断に関しては非常に精密であるが、それとは対照的に絶対的な判断に関しては驚くほど大まかである。たとえば十分な時間間隔をはさんで、周波数の異なるいくつかの音をランダムな順序で提示し、被験者にそれぞれの音を高さに関して分類させるというような、絶対的識別実験をやってみると、混同なしに区別できる音の高さのカテゴリー数はせいぜい7個程度であるという結果が報告されている(Pollack, 1952)。このような識別可能なカテゴリーの限界は、音の高さに限らず、たとえば音の大きさ、線分の長さ、光の明るさ、味、重さなどの感覚においても同じように見られる。Miller (1956)は、「マジカル・ナンバー7±2」というタイトルの論文で、さまざまな感覚における絶対的識別実験の結果を総括し、このような限界は、人間の一般的な情報処理能力の限界を反映したものと解釈した。その中で彼は、人間の感覚系の情報伝達量はおよそ 2.8ビットであると述べている (22.8=7)。
音の高さの比較判断では、われわれは第1の音の高さを短期記憶の中に保持しているので、その記憶と第2の音の高さとを直接比較することができ、精密な弁別ができる。しかし絶対的識別では、比較参照すべき音の高さは記憶の中にはないので、大まかな段階づけ程度のことしかできない。われわれは、音の高さや大きさ、光の明るさ、線分の長さ、円の大きさなどの感覚に関しては、絶対的、固定的な基準を心の中に持ち合わせていないのである。
しかし音の高さに関して、絶対的、固定的な基準を持っていて、提示された単一の音の音楽的音名を即座に答えたり、あるいは逆に指定された音名の高さを歌ったりすることができる人々がいる。このような能力は絶対音感(absolute pitch)と呼ばれ、古くから特殊な能力として音楽関係者には知られていた。また心理学者も、そのような特殊な能力に注目し、多くの実証的な研究が行なわれてきた (たとえば Stumpf, 1883; Revesz, 1913; Wellek, 1963)。
しかし音楽の音高体系は本来絶対的なものではなく、相対的な関係の上に成立するものである。絶対音感を持たない普通の人は、音楽的音高を絶対的に知覚することはできないが、相対的にとらえることはできるので、音楽をやる上でなんら支障はない。すなわち、ある基準の音が与えられて、それに基づいた相対的な音高関係の意識 (調性的文脈) が確立されたとき、われわれはそのような文脈を認知的スキーマとして用いて音楽的な音の高さをとらえることができるのである。このような相対的な音高の枠組みの中で音の高さをとらえる能力は相対音感(relative pitch)と呼ばれる。
絶対音感は、音楽的才能と関連するめざましい音楽的能力の1つと考えられてきた。その保有者は、単独の音の音名を正しく答えることができるという点で、普通の人にはできない特殊な能力を持っていると考えられがちである。しかしより正確に言えば、絶対音感保有者は、上で定義したような意味での音楽的高さを固定的に内在化しているという点できわめて特殊なのである。絶対音感はないが、優れた相対音感を持っている人は、相対的な音高の枠組みを自由にどのような高さにでもスライドさせることができる。このような相対性が、音楽的高さの本質的特徴でもある。絶対音感保有者の多くは、おそらく幼児期の初期学習によってその特殊な能力を身につけたものと考えられているが (Shuter-Dyson & Gabriel, 1981)、そのために音高の枠組みが固定してしまい、自由にそれをスライドさせる相対音感を発達させないでしまった人々であるとも言える。このようにみてくると、絶対音感は、非凡な能力と言うよりは、むしろ能力の欠如を意味しているという見方もできるであろう。
従来の絶対音感についての研究は、それが遺伝によるものか、あるいは学習によって習得可能なものなのかという点にのみ研究者の関心が向けられることが多かった (Meyer, 1899; Wedell, 1934; Brady, 1970; Cuddy, 1968, 1970)。しかし絶対音感保有者がどのように音楽的高さをとらえているのかという基本的な問題は、まだあまり明らかにはなっていない。
本研究は、絶対音感保有者、および比較のために絶対音感非保有者が、単音の音高 (絶対音高)、および音程、メロディ、和声などの音高関係をどのように認知しているのかを明らかにする目的で行われた継続的な研究の一部である。
2. これまでの研究の成果
2.1 絶対音感の正確さ
絶対音感についての研究で古くから用いられてきた最も基本的な測定方法は、ピアノ (またはその他の楽器) で、ある音域内の音を1つずつランダムに被験者に提示して、それぞれの音名とオクターブ位置を判断させるというものである。この方法を用いて、絶対音感保有者の音高識別の正確さを測定した (Miyazaki, 1989)。提示されたのは C1 (32.7 Hz) から B7 (3971.1 Hz) の範囲内の7オクターブにわたる84音で、被験者は音楽用の鍵盤の該当するキーを押すことによって音名を反応した。被験者は、予備テストで絶対音感を持っていることがわかっている音楽専攻学生7人である。
Figure 1 に、被験者の反応の分布パターンを示す。多くの反応が、左下から右上にかけての対角線にそって集中しており、絶対音感を持つ被験者が、提示された音の音名とオクターブ位置を正しく答えていたことを示している。これと別に対角線をはさんで両側にも平行に反応が並んでいるのが注目される。これらは「オクターブ・エラー」として知られているもので、音名の点では正しいが、オクターブの位置づけが誤っている反応である。オクターブ・エラーは、絶対音感保有者の絶対音高識別に見られる特有の反応であることが知られている (Bachem, 1950)。このことから、絶対音感保有者が直接的に知覚できるのはピッチクラス (オクターブ内の音の位置) であり、オクターブ間の位置 (pitch height) の判断は比較的不正確であることがわかる。
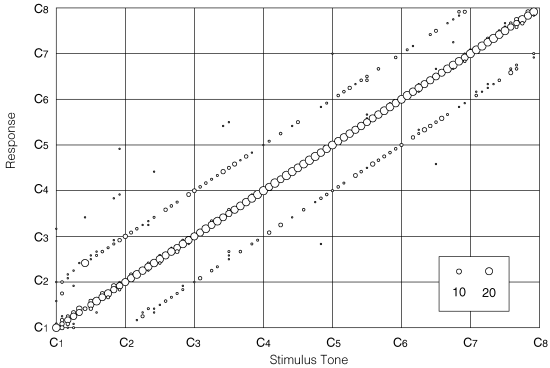
Figure 1. Scatter pattern of responses as a function of stimulus tones from 7 absolute-pitch listeners in the piano tone condition. The area of each circle is proportional to the number of responses to corresponding notes.
絶対音感を持たない被験者の反応はFigure 2のようになる。反応は左下から右上にかけて広く散らばっており、絶対音感保有者の反応分布との違いは明らかである。音高名判断課題で被験者はピッチの2つの側面、すなわちピッチクラス (pitch class) とピッチハイト (pitch height) に基づいて反応したと考えられる (Ward & Burns, 1982)。絶対音感を持たない被験者は、ピッチクラスを知覚することはできないが、不正確なピッチハイト (1次元的な周波数連続体上の位置の感覚や、一種の音色的特性など) に基づいて、音をオクターブ・カテゴリー程度にごく大まかに分類することはできると言える。これに対して絶対音感を持つ被験者はピッチクラスを知覚することができるので、まず音のピッチクラスを判断し、それからそのオクターブ位置を判断するという2段階プロセスを用いたものと考えられる。絶対音感を持つ被験者のピッチクラスの判断はきわめて正確であるが、ピッチハイトの判断の方は、オクターブエラーが多く見られたことからもわかるように、あまり正確とは言えない。ピッチハイトの判断の正確さに関する限り、絶対音感を持つ者と持たない者とはおそらく同じ程度と思われる。従って、絶対音感 (absolute pitch) という言い方は正確ではなく、absolute pitch classという用語の方が適切であると言えよう。
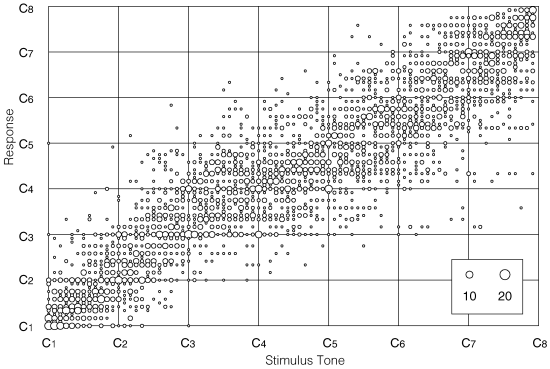
Figure 2. Scatter pattern of responses as a function of stimulus tones from 15 listeners without absolute pitch in the synthesized piano-tone condition. The area of each circle is proportional to the number of responses to corresponding notes.
2.2 絶対音高認知における音色と音域の効果
絶対音高判断の正確さは、さまざまな刺激要因による影響を受ける。その中で最も重要な要因は音色と音域である (Miyazaki, 1989)。Figure 3に、ピアノ音、FM音源のシンセサイザによる合成ピアノ音、純音の3種類の音色の音を刺激音として用いた場合の音高名判断のオクターブ位置ごとの正答率を示した。この図から、音名識別成績における、刺激音の音色と音域の効果が明かである。音色別の全体の正答率はピアノ音に対してが最も高く94.9%、純音に対してが最も低く74.4%、合成ピアノ音に対しては両者の中間で84.3%であった。反応は中央の音域が最も正確で、両端の音域にいくほど不正確になっていく傾向が見られる (特に高い音域よりも低い音域の方が正反応率の低下が著しい)。また音色とオクターブ位置の間には交互作用効果が見られ、純音に対する正反応率は、低い音域では合成ピアノ音よりも低いが、高い音域になると逆にわずかではあるが高くなっている。
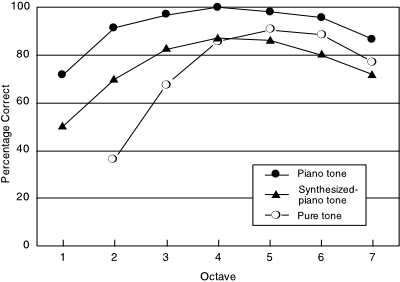
Figure 3. Percentage of correct responses obtained from seven AP subjects as a function of octave position (pitch region) for three different timbres. The percentage represents the overall proportion of the correct responses that occurred in 12 notes, from the C through the B above, within each octave range. The octave posision 4 corresponds to the pitch region from C.
2.3 絶対音高認知における白鍵音と黒鍵音の差別化
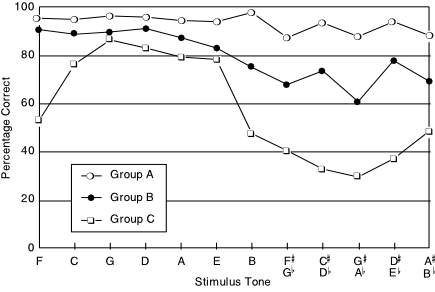
Figure 4. Percentage of correct responses in identifying 12 pitch classes by different levels of absolute-pitch subjets.Subjects in Group A (n = 10) are the most accurate (more than 90% correct), those in Group B (n = 12) are moderately accurate (70-90% correct), and those in Group C (n = 10) are the least accurate (less than 70% correct).
絶対音高判断の正確さと反応の速さは、ピッチクラスによって違いがある (Miyazaki, 1990)。Figure 4は、刺激音のピッチクラスごとの正答率を示したものである。反応の正確さに従って、被験者は3グループに分けられている。
・Aグループ (10人、正答率 90%以上)
・Bグループ (12人、正答率 70−90%)
・Cグループ (10人、正答率 70%未満)
一般に、ピアノの黒鍵音 (臨時記号がついた音) は白鍵音 (臨時記号がつかない音) よりも判断が不正確である。この傾向は不正確な絶対音感グループ (Cグループ) で最も顕著に見られる。白鍵音に関しては、3グループの間で正答率にそう大きな違いはないが、黒鍵音ではグループ間の違いが大きい。
刺激音のピッチクラスごとの反応時間の平均は、反応の正確さと裏返しの関係にある。すなわち、正確な絶対音感のAグループ (平均 0.605 sec) は反応が最も速く、不正確な絶対音感のCグループ (1.167 sec) が最も遅い。中程度に正確なBグループ (0.717 sec) は両者の中間である。また正確に判断された白鍵音に対しては反応が速く、エラーが多く見られた黒鍵音に対しては反応が遅い。このような白鍵音と黒鍵音の間の反応速度の違いは、Takeuchi & Hulse (1991) によっても確認された。
音高名判断におけるこのようなピッチクラス間の違いをもっと詳細に検討する。Figure 5a はAグループについて、提示された刺激音に対して各ピッチクラスの反応が起こった回数を示している。このグループは正確な絶対音感のグループであるので、エラーの数はきわめて少なく、それもほとんどが1半音のエラーである。Figure 5b は、不正確なCグループの反応パターンである。このグループの反応には多くのエラーが見られるが、興味深いのは、隣り合う白鍵音と黒鍵音の間のエラーが非対称であるという点である。すなわち、白鍵音が隣の黒鍵音と混同されることは比較的少ないが、逆に黒鍵音が隣の白鍵音と混同されることが多い。たとえば、Cの刺激音をC#と判断したエラーの数は17、DをC#と判断したエラーは8であるのに対して、C#の刺激音をCと判断したエラーは62、Dとしたエラーは44に達している。
Figure 5c に示したのは、非対称的なエラーを最も鮮明に示した被験者の刺激−反応パターンである。この被験者は白鍵音はほとんど完全に正しく答えているが、黒鍵音はほとんどがまったく同定できないという特異なパターンを見せている。たとえば、C#が20回提示されたうち、18回はCと、2回はDとする反応が起こっていて、正しいC#という反応は1回もない。またF#は常にFと判断されている。これらの結果から、絶対音感保有者、特に不正確な絶対音感保有者の中には、白鍵音についてだけの絶対音感を持つ者がいると言える。このような絶対音感のタイプを部分的絶対音感と呼ぶことができる。こうした反応のかたよりは、表面的には反応バイアスを表しているように見える。しかしこれはむしろ知覚バイアスと見なすべきであろう。すなわち、不正確な絶対音感保有者では、黒鍵音のピッチクラスは記憶の中に安定的に確立されておらず、そのために隣接する白鍵音と混同されることが多いと解釈される。
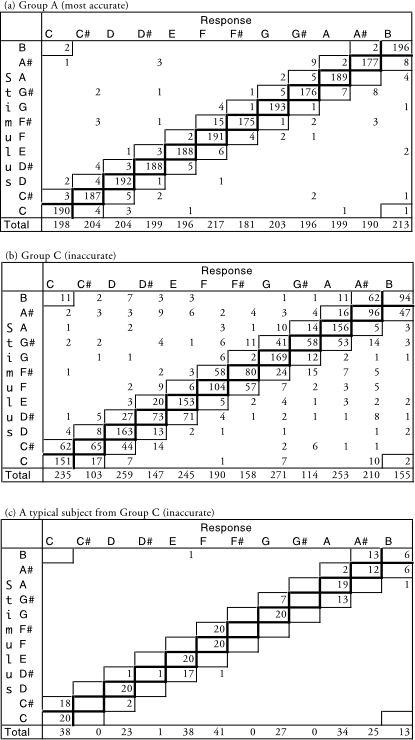
Figure 5a-c. Stimulus-response matrices of absolute-pitch test
このような結果のパターンは、発達初期の絶対音感獲得過程と関連があると言える。絶対音感保有者のほとんどは、早期の音楽訓練 (主としてピアノのレッスン) を通じて絶対音感を獲得したものと考えられる。このような訓練の中では、白鍵音の絶対音感は黒鍵音のそれよりも成立しやすい。ピアノのレッスンは通常ハ長調の音階や曲を弾くことから始まるので、レッスンの最初の段階では、子供たちは白鍵音をより多く耳にすることになる。絶対音感を獲得することが最も効果的な時期は3歳から6歳ころまでと考えられるが 、黒鍵音は白鍵音の後に徐々に導入されるので、この期間に黒鍵音を耳にする機会は白鍵音よりもずっと少ない。あるいは黒鍵音がピアノのレッスンの中に入ってくる頃には、絶対音感を獲得するのに最も効果的な時期を過ぎてしまっているということもあるだろう。このようにして、白鍵音についてだけ絶対音感を獲得したが、黒鍵音の絶対音感は不正確であったり、まったく獲得されていない部分的絶対音感が成立するものと考えられる。
2. 4 絶対音感保有者の音程の知覚
音楽が相対音高の上に構築されるものであり、絶対音高よりも相対音高の方がはるかに重要であることには疑問の余地はない。相対音高にくらべれば、絶対音高は音楽にとって本質的なものではない。たとえば楽器や声を基準音高に合わせるときには、たしかに絶対音高が問題になる。このような場合、音楽家が絶対音感を持っていると人間音叉としては役に立つかもしれないが、それ以上に意味があることではない。絶対音感は音楽にとってなくてもかまわないものなのである。
ところが絶対音感は相対音感と両立しない面を持っており、一方が他方の発達を妨害するという可能性がある。子どもの認知発達過程の一般的な特徴の一つとして、ピッチを絶対的に把握するやり方から相対的に把握するやり方にバランスシフトが起こると考えられる (Sergeant & Roche, 1973)。絶対音感の獲得が6歳を過ぎると次第に困難になっていくのは、その頃から相対音感が発達し始めて、ピッチを固定的にではなく、相対的にとらえるようになるからである。これとは逆に、絶対音感は音楽的ピッチ情報の処理にとってある意味で好ましくない影響をもたらすことがあるかもしれない。もし子どもが幼児期の訓練によって絶対音感の能力を獲得した場合、以後の音楽活動においてその能力に依存する傾向が生まれ、ある場合には、相対音感を学習する動機づけを失うことになるかもしれないからである。その結果、子どもがいったん絶対音感を獲得すると、相対音感を発達させるための特別の注意がはらわれない限り、相対音感の完全な発達が阻害される可能性が指摘できるだろう。もしこのようなことがあるとすると、絶対音感を持つことが、相対音高課題の遂行に不利に働くことがあると予想される。このことを実験的に検討した (Miyazaki, 1993)。
被験者には、2つの和音系列と、それに続いて旋律的音程をなす2音が提示される。最初の和音系列は、被験者の中に、ある特定の調性の枠組みを確立させるためのコンテクスト刺激で、1つの調の属七和音 (V7) と主和音 (I) からなるカデンツである。これに続いて提示される2音のうちの第1音は、常に、和音系列により確立された調の主音であり、第1音に対して第2音 (ターゲット) はさまざまな音程関係にある音である。和音系列で確立される調は、ハ長調 (C major)、嬰ヘ長調 (F# major)、そしてホ音 (E) よりも1/4音低い音を主音とする長調 (E- majorと表す) の3種類である。ターゲット音程は260セント (短3度よりも少し小さい) から540セント (完全4度よりも少し大きい) までの範囲内にある20セント間隔の15種類である。pitch heightの影響をなくすために、オクターブ間隔の8個の倍音から構成される釣り鐘型のスペクトル包絡を持つ複合音 (Shepard, 1964) を刺激音として用いた。被験者は、和音系列によって確立された調の中で2音を聞いて、第1音 (調の主音) に対して第2音が、短3度 (ミ-フラット)、長3度 (ミ)、完全4度 (ファ) のどれに聞こえるかを判断した。
被験者は、絶対音感の正確さによって次のような4グループに分けられた。
(A) 正確な絶対音感グループ (15人). 60試行の絶対音感テストの正答率が90%以上
(B) 部分的絶対音感グループ (16人). 白鍵音は正確に判断できるが、黒鍵音をとなりの白鍵音と混同する間違いが多い。エラーのほとんどが半音のエラーなので、それらと正答をたすと90%以上になる。
(C) 不正確な絶対音感グループ (9人). 全般にエラーが多く、正答率が40-80%
(D) 非絶対音感グループ (15人). 絶対音感テストの正答率は40%未満であるが、絶対音感グループと同等の音楽経験を有する。
Figure 6 は、各調性コンテクスト条件における音程識別の正答率 (棒グラフ) と反応時間 (折れ線グラフ) を、被験者グループ別に表したものである。なお正答率は、等分平均律で定められる短3度、長3度、完全4度の大きさ (300, 400, 500セント) を中心にして、±40セントの範囲を、それぞれの音程の許容範囲として計算した。たとえば、360−440セントの範囲の刺激音程に対して長3度と答える反応が正反応として数えられた。絶対音感の3グループは、Cのコンテクストにくらべて、E-とF#のコンテクストでの正答率が低くなっている。特に、部分的絶対音感グループは、C以外のコンテクストの正答率が3グループの中で目立って低くなっていることが注目される。部分的絶対音感グループの被験者の絶対音感は、この課題で役に立つほど正確ではなかったが、相対音高の発達を阻害するほどには正確だったのかもしれない。
これに対して、非絶対音感グループの被験者は、どのコンテクスト条件においても、ほとんど同じくらいに正確な判断をしている。C条件では4群の正答率はほとんど同じ程度であるが、E-とF#条件での正答率は、非絶対音感群の方が絶対音感群よりもかなり高くなっている。
反応時間も正答率と一致した傾向を示している。非絶対音感群は、どのコンテクスト条件でも、最も反応が速い。これにくらべて絶対音感群は反応が比較的遅く、またC条件にくらべてE-とF#条件で反応時間が目立って長くなっているのがわかる。
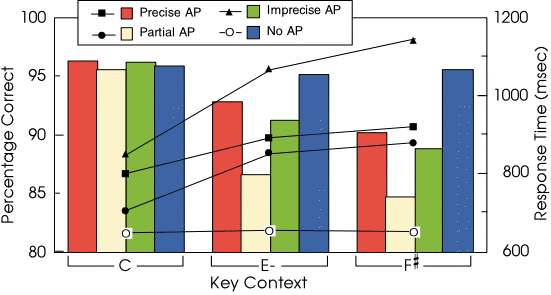
Figure 6. Average percentage of correct responses (columns) and response time (lines) as a function of key context.
音程識別の正確さは、特に絶対音感群の被験者のE-とF#条件でかなりの個人差があり、グループ・データだけでは正確なところが見えてこないので、Figure 7a-d に異なるコンテクストにおける個人の正答率を各グループ別に示す。絶対音感群の何人かの被験者は、どの調性条件でも正確に音程を識別しているが、絶対音感群のおよそ半数の被験者は、C条件にくらべてE-とF#の条件で明らかに正答率が低下している。これは非絶対音感群が、どの調性条件でも同じくらいの高い正答率を示していることと明らかな違いである。
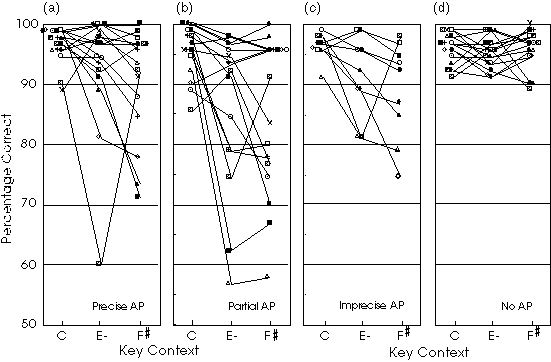
Figure 7a-d. Percentage of correct responses of individual listeners as a function of key context.
Figure 8a-b に、2人の典型的な被験者の識別反応パターンを示す。3つのパネルはそれぞれ異なる調性条件の結果を示しており、提示された音程の大きさに関して、短3度 (m3)、長3度 (M3)、完全4度 (P4) の反応が起こった回数が識別曲線の形で表してある。(a) は、正確な絶対音感を持つ被験者の反応の分布である。CとE-の条件では、音程識別は比較的正確に行われているが、F#条件では識別がほとんどできなくなっている。(b) は部分的絶対音感群の被験者である。C条件では識別は比較的正確であるが、E-とF#の条件では識別曲線がほとんど重なり合っており、音程をまったく区別できていないことがわかる。これらの被験者が子どもの頃から現在まで音楽の訓練を受けてきているということを考えると、このようにC以外の調性条件で、短3度、長3度、完全4度の基本的な音程がほとんど識別できなくなってしまうという結果はほとんど信じられないくらいのものと言える。
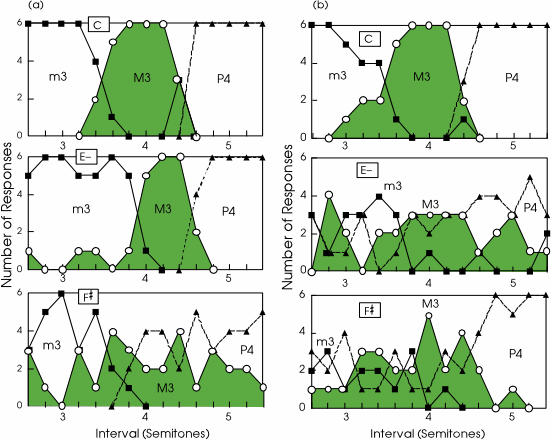
Figure 8a-b. Identification functions of two selected absolute-pitch listeners who gave typical results.
2.5 絶対音感保有者の割合
今まで音楽専攻学生を被験者にして行ってきた絶対音感テストの結果から、音楽学生における絶対音感保有者の割合を推定した。Figure 9 は、京都市立芸術大学の音楽学部の学生 36人、新潟大学教育学部の音楽教員養成過程の学生 37人、ワルシャワのショパン音楽アカデミーの学生 27人について、絶対音感保有者の割合を示したものである (ただしこれは、後述する別の目的の実験のために予備的に行った絶対音感テストの結果であり、サンプル数も少ないので、ごくおおまかな目安にすぎないが、だいたいの傾向はわかるだろう)。この図から、音高名判断の正答率が90%以上の正確な絶対音感保有者の割合は、ショパン音楽アカデミーの学生では11%であるのに対して、日本の音楽学生では約30%に達している。50%以上の正答率の割合で見ると、ショパン音楽アカデミーでは30%程度でしかないのに対して、京都市立芸大では70%、新潟大学でも50%近くにのぼる。
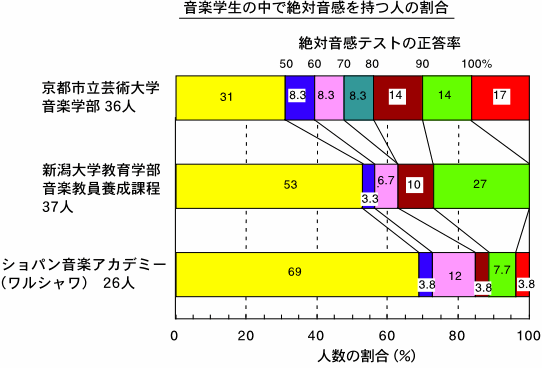
Figure 9. Percentage of absolute pitch possession
絶対音感保有者が一般の人々の中で、あるいは音楽家の中でどのくらいの割合を占めるのかについては、正確な調査がなく、また絶対音感の定義の仕方や測定方法によって推定値はちがったものになるので、はっきりとしたことは言えない。しかし多くの研究者は絶対音感保有者の割合をきわめて低く推定しており、一般人の間では0.1%, 音楽家でもせいぜい10%以下であるとされている (Bachem, 1955; R思市z, 1913; Wellek, 1963)。現在の日本で絶対音感保有者の割合が高いという事実は、絶対音感が非常にめずらしい特別の能力であるという通説をくつがえすものである。このように日本で絶対音感保有者の割合が高いのは、明らかに、早期の音楽教育が広く行われていることと、絶対音感を育てることを目的とする音楽教室が存在することによる。さらに、音楽以外の分野に進んだ人々の中にも、音楽を専門とする人々ほどではないが、絶対音感を持つ者が少なくないということも日本だけに見られる特異な現象と言える。このような現象が見られるのは、幼児期のピアノのレッスンの中で絶対音感を獲得したが、その後、音楽以外の道に進んだ人々が少なくないからである。しかしこのように絶対音感の能力を持つ人々が多いということは日本の音楽教育が誇るべきことなのかどうかは、後述する実験の結果を考えるときわめて疑わしい。
3. メロディの認知
音程識別の実験では、さまざまに異なる高さの基準音とターゲット音が継起的に提示され、被験者は基準音に対するターゲット音の相対音高名 (音程名) を判断するという課題を行った。その結果、絶対音感非保有者は、基準音がどの高さであっても同じ水準の識別成績を示したのに対して、絶対音感保有者は基準音がC音の時には絶対音感を利用して正確な反応をすることができたものの、基準音がC以外の音の場合には判断がきわめて不正確になり、反応時間も長くなるということが見出された。絶対音感保有者の音程識別成績が非保有者にくらべて不正確だったという結果は、絶対音感保有者が、相対音感を用いるべき課題でも絶対音感を用い続けるという不適切なストラテジに固執していたことを示している。絶対音感と相対音感は異なる音高処理様式であり、両者は両立しない場合があることがこの実験の結果から示唆される。絶対音感を持っていると相対音感もすぐれているとは必ずしも言えず、むしろ絶対音感が、相対音感を用いる聞き方や相対音感の発達を妨げるように働くことがあるのではないかと考えられる。
しかし音程は2音の間の音高関係であり、音楽的音高関係としては最も単純なものに過ぎない。そこでこの研究では、より音楽的な状況としてメロディの中の音高関係を絶対音感保有者がどのように処理しているのかを検討する。メロディの同一性は、音程と同様に、それを構成している音の間の音高関係によって決まる。従って、ある1つのメロディは、どの高さから始まっても、その構成音の音程関係が保たれている限りは同じメロディとして認知されるはずのものである。1つの曲を異なる高さで演奏することを音楽では移調と言うが、移調されても曲の同一性が損なわれることはないということは音楽の基本的原則である。このことはまた、移調のもとでの等価性というゲシュタルト知覚の基本法則の1つとして心理学的にも受け入れられており、人間の知覚の一般的特性の一つと考えられる。このような意味で、メロディの同一性は、それを構成している音の絶対音高ではなく、それらの間の音高関係、あるいは一定の音高コンテクストの中での音の動きによって決まる。我々に最もなじみのものである西洋調性音楽では、調性構造がこのような音高コンテクストをなしており、長調や短調などの音階の中での音の位置づけや音の動きが、音楽の本質であると言える。従ってこうした音高コンテクストの中で音の関係をとらえることが、音楽を理解するための基本的前提であり、個々の音の絶対音高は音楽的には重要ではない。
音程識別実験で見られたように、もし絶対音感保有者が絶対音感に強く依存する傾向があって、相対音高をとらえるのに困難を感じることがあるとすると、移調されたメロディを知覚する際にも、絶対音感は同様の不利な結果を生じることが予想される。音程の知覚成績が調によって違ったり、メロディが移調されると認知成績が低下したりするということが絶対音感保有者に顕著に見られるとすると、これは一般に認められているメロディの移調同一性の原則が絶対音感保有者の場合には成り立たないということになる。
3.1 実験1
この実験では、メロディ知覚の研究 (たとえばDowling, 1978) でよく用いられているメロディの移調再認の手続きを用いる。短い標準メロディに続いて比較メロディが順に提示さる。比較メロディは標準メロディを移調したものであるが、相対音高の点ではこれらはまったく同じか、あるいは1音だけ高さが変化している。被験者の課題は、異なる調で提示されたこれら2つのメロディが同じか違うかを判断することである。
〈方法〉
刺激 実験で提示される刺激を Figure 10 に示す。各試行では標準メロディと比較メロディが順に提示されるが、どちらのメロディも等分平均律の全音階的長音階 (標準音高はA4=440 Hz) からとられた7音からできている。標準メロディは常にハ長調の調性で、比較メロディはハ長調 (C), 嬰ヘ長調 (F#), 1/4音低いホ長調 (E-) の3通りの調性で出され、各メロディの第1音は常にその調の主音である。またそのメロディの調性を確立させるためのコンテクスト刺激として、各メロディの前には属7和音 (V7) と主和音 (I) の2つの和音 (カデンツ) がおかれている。標準メロディは、G3−A4の範囲内の全音階音を並べて作ったもので、音程の跳躍は最大で長6度までである。比較メロディは、標準メロディと同じか、または最初と最後の音を除く5音のうちのどれか1つの音が、音階の隣の音に変化している (音階内の音の位置によって、変化幅は半音の場合と全音の場合とがある)。ただしこの操作によってメロディの輪郭 (音高の上行・下降のパターン) が変化することがないようにした。刺激系列のテンポは4分音符=180で、2分音符 (667 msの長さ) の和音2つから成る第1のカデンツのあと、和音1つ分の長さの休止をはさんで標準メロディが続く。メロディは4分音符 (330 ms) の長さの音からできている。その後1 sの時間間隔をはさんで、第2のカデンツと比較メロディが同じタイミングで提示される。 比較メロディが終わってから次の試行が始まるまで4 sの時間があり、この間に被験者は反応する。標準メロディとして30種類の異なるメロディを作成し、同じメロディセットを3種類の調性条件で用いた。標準メロディと比較メロディの30セットのうち16セットは相対音高の点で同じメロディの組であり、残りの14 セットは異なるメロディの組である。
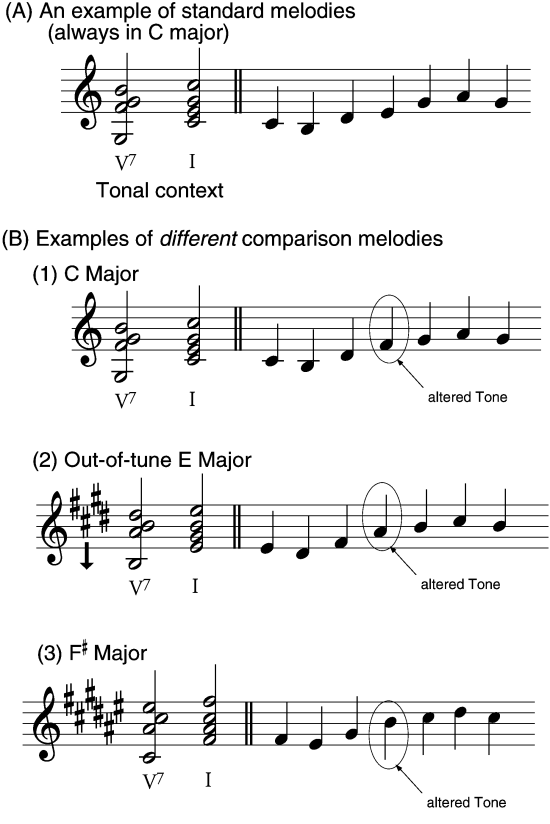
Figure 10. Examples of stimuli presented in Experiment 1
装置 刺激音の発生と被験者の反応の取り込みは、コンピュータ (Apple, Macintosh IIci) とそれに接続したMIDIインタフェース (Mark of the Unicorn, MIDI TimePiece II) によるMIDIシステムを用いて行われた。刺激系列は、Macintosh 上で動作するシークエンサ・ソフトウェア (Mark of the Unicorn, Performer) を用いて作成され、トーンジェネレータ (Yamaha TX-1P) のピアノ音でスピーカ (Yamaha NS-1000M) から被験者に適度な大きさで提示された。被験者は音楽用鍵盤 (Yamaha KX-88) の「同じ」と「違う」というラベルがはられた2つのキーのどちらかを押すことによって反応した。被験者の反応は、鍵盤からのMIDI信号としてシークエンサ・ソフトウェアを用いてコンピュータに取り込み、反応の正誤を判定するとともに、反応時間を測定した。ここで測定した反応時間は、メロディの最後の音が鳴ってから被験者がキーを押すまでの時間である。被験者の課題は比較メロディが標準メロディと同じか違うかを判断することであるので、違うメロディの場合には比較メロディの中の変化した音が現れた時、同じメロディの場合には比較メロディの中に変化音がないことが明らかになった時が、反応時間の計測を開始する時点として適切かもしれない。従ってメロディの最後の音から反応時間の計測を開始すると、メロディの途中で被験者が反応した場合には反応時間はマイナスの値になってしまう。しかしここでは反応の速さそのものが問題なのではなく、絶対音感群と非絶対音感群の間の反応の速さの比較が重要なので、比較メロディの最後の音から反応生起までの時間を反応時間として測定することで問題はないと思われる。実際にはメロディの途中で変化音が現れた場合でも、メロディを最後まで聞いてメロディ全体の形を比較することによって判断する被験者が多く、マイナスの反応時間を示した例はごく少なかった。
手続き 被験者の課題は、異なる高さで聞こえてくる2つのメロディが、完全に同じか、少し変化しているかを判断して、できるだけ速く該当する反応キーを押すことである。実験開始に先立って被験者には、2つのメロディが異なる高さで出てくる (従ってメロディを作っている音の絶対音高はすべて変化する) が、それらの音程関係が保たれているならば、音楽的には同じメロディと見なされるということを、よく知られたメロディを例として用いて説明し、実際に同じメロディの例と変化したメロディの例を聞かせて、実験課題を理解させた。また比較メロディの途中でそれが標準メロディと違うということがわかったら、メロディが終わるのを待たずにできるだけ速く反応するように指示した。同試行と変化試行3回ずつの練習試行を行なった後に、本試行を開始した。本試行は全90試行から成り、3種類の調性条件が予測できない順序で試行ごとに交代するように順序づけた。
被験者 被験者は28人で、全員が新潟大学教育学部音楽教員養成課程の学生である。あらかじめ行った絶対音感テストの結果から、絶対音感保有者15人 (許容範囲1半音とした時の正答率90%以上、平均98%) と非保有者13人 (許容範囲なしの正答率60%以下、平均21%) に分けられる。
〈結果〉
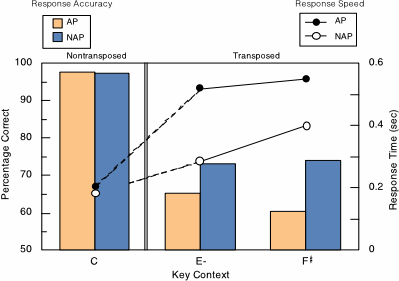
Figure 11. Response accuracy (columns) and speed (lines) in recognizing transposed melodies in different key contexts.
絶対音感群と非絶対音感群のそれぞれについて、各調性条件におけるメロディの比較判断の正確さをFigure 11 の棒グラフに示す。被験者の反応は「同じ」か「ちがう」かのどちらかなので、反応のチャンスレベルは50%になる。2つのメロディを同じ高さで比較できる同一調 (C major) の条件では、どちらのグループでも判断の正確さはほとんど上限近くに達しているのにくらべて、比較メロディが標準メロディと異なる調に移調されて提示されるE-とF#の移調条件では、どちらのグループも再認成績が低くなっている。絶対音感レベルを被験者間要因、調性条件を被験者内要因とする2要因分散分析の結果によると、絶対音感レベルの主効果 [F(1, 26)=6.99, p<.02]、調性コンテクストの主効果 [F(2, 52)=144.72, p<.001]、両者の交互作用 [F(2, 52)=6.33, p<.005] がすべて有意であった。交互作用が有意だったことは、同一調条件では絶対音感群と非絶対音感群の正反応率に差はないが、移調条件では非絶対音感群にくらべて絶対音感群の方が反応が不正確になっていることを示している。
この実験の目的にとって重要なことは、メロディを異なる調性で比較しなければならない移調条件における絶対音感群と非絶対音感群の間の遂行成績の比較である。そこで移調条件のみについて分散分析を行った。その結果、絶対音感レベルの主効果が有意であったのに対して [F(1, 26)=8.09, p<.01]、調性コンテクストの主効果 [F(1, 26)=1.14, p=.30]と、両者の交互作用はどちらも有意ではなかった [F(1, 26)=2.65, p=.12]。このことから、どちらの移調条件においても、絶対音感群は非絶対音感群にくらべてメロディの比較判断が不正確であり、またどちらのグループでもE-条件とF#条件の間で正確さに有意な違いはないと言える。
この関連をより詳細に見るために、Figure 12に、各被験者ごとに移調条件でのメロディ再認の正答率と絶対音感テストの得点との関連を示す。非絶対音感群の被験者 (グラフの○印) は、メロディ再認成績がほぼ完ぺきに近い者からほとんどチャンスレベルに近い者まで非常に広い範囲にわたっているのに対して、絶対音感群の被験者 (グラフの●印) は比較的低い成績の範囲に集まっている。相関係数は r=−.458であり、メロディ再認テストと絶対音感テストの成績の間には、有意な負の相関があると言える (n=28, p<.02)。
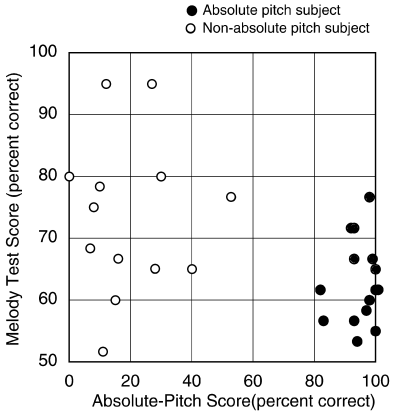
Figure 12. Scattergram showing the correlation between the accuracy of transposed melodiesrecognition and the absolute-pitch accuracy.
反応時間の結果 (Figure 11 の折れ線グラフ) でも正反応率と同様の傾向があり、同一調 (C major) 条件の反応が最も速い。またこの条件では絶対音感群と非絶対音感群の間では速さにほとんど違いはない。これにくらべて2つの移調条件では反応時間が長くなっており、さらに非絶対音感群にくらべて絶対音感群の反応が遅くなっているように見える。絶対音感レベルを被験者間要因、調性条件を被験者内要因とする2要因分散分析の結果によると、絶対音感レベルの主効果は有意ではなく [F(1, 26)=1.52, p>.2]、調性コンテクストの主効果 [F(2, 52)=40.68, p<.001] と両要因の交互作用 [F(2, 52)=5.40, p<.01] が有意であった。交互作用が有意だったことは、同一調条件では絶対音感群と非絶対音感群の反応時間に差がないのに対して、移調条件では非絶対音感群にくらべて絶対音感群の方が反応時間が長くなっていることを示している。しかし移調条件のみについて分散分析を行ったところ、個人差がかなり大きいこともあって絶対音感レベルの主効果は有意な水準には達しなかった [F(1, 26)=2.15, p>.1]。また調性コンテクストの主効果 [F(1, 26)=0.97] も絶対音感レベル×調性コンテクストの交互作用も [F(1, 26)=0.07] ともに有意ではなかった。従って、反応時間は絶対音感群と非絶対音感群の間で違いがあるとは言えない。
〈考察〉
3つの調性条件のうち同一調 (C major) の条件では、比較メロディが標準メロディと同じ高さから始まる。2つのメロディが同じ場合には同じ音高の音が同じ順序で現れ、異なるメロディの場合には1つの音だけが異なる高さで現れることになる。このような場合には、標準メロディを作っている音の絶対音高の短期記憶と、続いて現れる比較メロディ構成音の絶対音高とを直接的に比較することによって、2つのメロディの異同を判断することは容易である。実験の結果、同一調条件では絶対音感群と非絶対音感群のどちらもきわめて判断が正確であったことは、絶対音高の短期記憶が絶対音感とは無関係な一般的な能力であることを反映したものと言える。
これに対して移調条件 (E- majorとF# major) では、比較メロディは標準メロディと異なる高さで現れるので、2つのメロディの対応する音の絶対音高はすべて異なることになる。従って移調条件では、絶対音高を直接的に比較するやり方は役に立たない。すなわち移調条件の場合には、絶対音高という知覚的な性質を捨象し、メロディを構成している音の相対音高 (音程) を符号化してそれに関して2つのメロディを比較しなければならない。このように移調条件の課題を行うのに必要な処理は同一調条件の課題で必要な処理とは根本的に異なる性質のものである。すなわち、絶対音高の短期記憶の符号化は直接的で容易であり、音楽経験にあまり大きく依存することはないが、相対音高の符号化は抽象化のレベルが高く、比較的困難であり、音楽経験に大きく依存するものと考えられる。
絶対音感群と非絶対音感群のどちらにおいても、同一調条件にくらべて移調条件の方が遂行成績が低くなった。しかし同一調条件は音高の短期記憶を用いて判断できる比較的簡単な課題であるのに対して、移調条件は2つの7音メロディの音高関係の記憶を必要とする複雑な課題であることから、このような遂行成績の違いは当然予想されたことであり、被験者内要因である調性コンテクストの効果はあまり重要ではない。
より重要な結果は、絶対音感を持つ被験者の方が絶対音感を持たない被験者よりも移調条件での遂行成績が低いことである。このように被験者群の間の遂行成績の比較が重要な場合には、比較する被験者群が音楽経験や音楽能力の点で同等でなければならない。さもないと、得られた結果が、被験者の音楽的遂行能力の違いに起因するものであって、絶対音感の有無によるものとは言えなくなってしまうからである。しかし絶対音感は幼児期の音楽訓練によって獲得される場合がほとんどであるため、絶対音感レベルと音楽経験・音楽的能力は関連がある。従って絶対音感群の方が非絶対音感群よりも遂行成績は高くなるはずである。ところがここで得られた結果はその逆であった。以前に行った音程識別実験 (Miyazaki, 1993) では、絶対音感保有者の中には、個々の音の絶対音高に拘束されて音程を音高関係としてとらえることがうまくできないものが少なくないことが明らかにされたが、実験1の結果は、メロディ再認においても、絶対音感保有者が音高関係を認知することがうまくできないことを示すものと言える。
3.2 実験2
実験1のように、2つのメロディが聴覚的に提示されて、それらの同異判断を行う再認実験では、同一調条件は上で述べたような理由から、移調条件の遂行成績を比較するための統制条件とはなり得ない。そのため実験1ではもっぱら被験者群間の遂行成績の違いを見るしかなかった。実験1の課題の問題点は、標準メロディと比較メロディがともに聴覚的に提示されるため、同一調条件はメロディの比較判断課題ではなく音高の短期記憶課題になってしまうという点であった。そこで実験2では、標準メロディを音としてはなく楽譜の形で視覚的に提示し、比較メロディは聴覚的に提示して、被験者は楽譜のメロディと聞こえてきたメロディが同じか違うかを判断するようにした。このような課題では、絶対音感保有者が絶対音感ストラテジに固執する場合には、同一調条件と移調条件の遂行成績に違いが見られるようになると考えられる。移調条件では絶対音感が妨害的に働いて、課題遂行が困難なものになると予想されるからである。これに対して、絶対音感と相対音感を使い分けられる被験者や、絶対音感を持たない被験者にとっては、同一調条件と移調条件は同等のものになると考えられる。
〈方法〉
手続き 実験課題は、標準刺激と比較刺激が同じか違うかを判断する異同判断課題である。被験者は13"モニター (Apple) とその手前におかれた反応用の鍵盤 (Kurzweil K-1000) に向かってすわる。被験者には2つの短いメロディーが異なるやり方で提示される 。第1のメロディー (標準メロディー) は楽譜の形でモニターの中央に視覚的に提示され、被験者は5秒間それを読んでリハーサルする。次に第2のメロディー (比較メロディー) が聴覚的に提示され、それが第1のメロディーと同じか違うかをできるだけ遠く判断することが被験者の課題である。被験者は鍵盤の「同じ」と「違う」というラベルをはられた2個のキーのどちらかを押すことによって反応した。被験者には、比較メロディーが標準メロディーと違うことがわかったら、メロディーが鳴り終わるまで待つことなく、できるだけ速く反応するように指示した。第1のメロディーの楽譜は、被験者が反応キーを押すまで、モニターに提示されたままになっている。比較メロディーが終わってから次の試行の開始までの時間は約8秒である。
刺激メロディーの発生、ならびに被験者の反応の取り込み (反応時間の計測を含む) にはApple Macintosh上で動作するシークエンサ・ソフトウェア (Mark of the Unicorn, Performer) を用いた。刺激音は、モニターの両側におかれたスピーカ (Bose, 501X) から適度な大きさで提示された。
刺激 Figure 13(A) に標準メロディの一例を示し、Figure 13(B) には3つの異なる調性条件ごとにdifferent試行での比較メロディの例を示した。標準メロディーは5音から成っていて、常にC majorで記譜され、F3-C5の範囲のC majorの音階構成音をランダムに配列することによって作られた。ただし常に音階の主音であるCから始まり、隣り合う音の間の音程が半音一完全4度の範囲内におさまるようにした。
標準メロディが画面にあらわれてから5秒後に、比較メロディーの調性スキーマをはっきりと確立できるようにするための定型的終止形をなす和音系列 (V7-I) が提示され、その後すぐ比較メロディーが続く。比較メロディは、標準メロディと同じC majorの同一調条件、1/4音低いEを主音とする長調 (E- major)、またはF# majorに標準メロディを移調した移調条件のうちのどれかで出され、毎試行予測できない順序で調が変化する。和音系列と比較メロディーはFigure 13 (B) のようなタイミングで提示された。テンポは4分音符 = 150、従ってメロディに先行する和音ひとつの持続時間は800 ms, メロディの1音あたりの持続時間は400 msec (最後の音だけが600 msec)、和音とメロディの間の時間間隔は800 msである。和音と比較メロディは、ピアノ音源 (Yamaha TX-1P) によるピアノに近い音で提示された。

Figure 13. Examples of the melodies presented in Experiment 2. (A) An example of standard melodies presented visually always in the C major notation; (B) Examples of different comparison melodies presented auditorily in the C major, out-of-tune E-flat (E-) major, or F-sharp major. Notes enclosed by ovals are varied tones.
提示される標準一比較メロディーの対は、比較メロディーの各調性条件につき20対あり、一人の被験者は全体で60回の判断を行うことになる。各調性条件の20対のメロディーのうち8対ではふたつのメロディーは相対音高に関して同じであり (same試行) 、残りの12対では異なっている (different試行)。different試行では、比較メロディーの第2, 第3, または第4音のどれかひとつが標準メロディーと比べて1音階ステップだけ高くまたは低く変化している。すなわち、変化音の音階内の位置によって、全音変化する場合と半音変化する場合とがある。ただしこの変化によって、比較メロディーの旋律輪郭が標準メロディーと異なるものになることのないようにした。
被験者 新潟大学教育学部の音楽教員養成課程の学生27人で、前もって行った絶対音感の予備テストの結果から、正答率が90%以上の正確な絶対音感群 (AP1群 9人)、50-86%の不正確な絶対音感群 (AP2群 9人)、40%以下の非絶対音感群 (NAP群 9人) に分けられた。
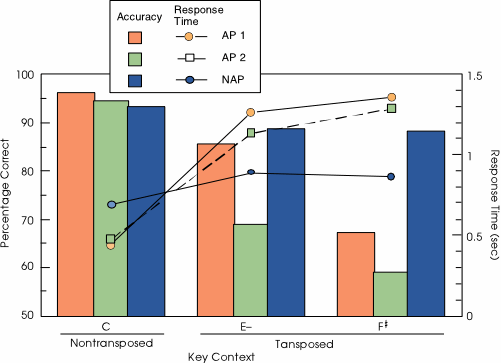
Figure 14. Average percentage correct responses (columns) and response times (lines) in three different key contexts (Experiment 2).
〈結果〉
反応の正確さ
絶対音感群 (AP1, AP2) と非絶対音感群 (NAP) の各調性条件における反応の正確さをFigure 14の棒グラフに示す。正反応率について、絶対音感群と非絶対音感群を分ける絶対音感レベルの要因を被験者間要因とし、調性条件を被験者内要因とする2要因分散分析を行った。その結果、絶対音感レベルの主効果 [F(2, 24)=26.01, p<.001]、調性の主効果 [F(2, 48)=55.05, p<.001]、これら2要因の間の交互作用 [F(2, 48)=10.29, p<.001] がすべて有意であった。交互作用が有意になったことは、調性条件の効果が絶対音感レベルが違う被験者群によって異なっていることを示している。すなわち非絶対音感群は、調性の要因の効果があまり見られず、どの調性条件でもほとんど同じくらい正確に判断している。これは移調のもとでの等価性の原則から見て当然の結果と言える。絶対音感を持たない被験者は、比較メロディがどの調で聞こえてきても、同じように楽譜との比較判断を行うことができるからである。これに対して絶対音感のAP1群とAP2群は、調性の効果が顕著に見られる。すなわち楽譜と同じC majorで比較メロディが出される場合にはきわめて正確に判断しているが、楽譜と異なる調で比較メロディが現れる条件では判断が不正確になっている。特にF# majorの条件で正答率の低下が著しく、ここではAP2群の正答率はチャンスレベルをわずかに上回る程度でしかないことが注目される。この結果、同一調条件では、絶対音感群は非絶対音感群を上回る高い正答率を示しているが、移調条件では逆に非絶対音感群の方が絶対音感群を上回っている。絶対音感群の被験者が幼児期から始まる長い音楽訓練を受けていることを考えると、移調条件においてこのように短い単純なメロディが楽譜と同じか違うかを判断することがこれほどまでにできないことには驚かされる。
絶対音感レベルと調性の間の交互作用が有意であったので、各被験者グループ別に1要因分散分析を行って、調性条件の効果を調べた。その結果、AP1群とAP2群のどちらにおいても、調性の効果が有意で [それぞれ F(2, 16) =25.92, p<.001; F(2, 16) =45.47, p<.001]、3つの調性条件の平均値の間の対比は、すべてが1%水準で有意になった。これに対して非絶対音感群では調性の効果は有意にはならなかった [F(2, 16) =1.16, p>.3]。この結果から、絶対音感群では、同一調条件にくらべて移調条件が遂行成績が低く、移調条件の中でもE- majorよりもF# majorの方がさらに成績が低い。一方、非絶対音感群の遂行成績はどの調性条件でも有意な差はないと言える。
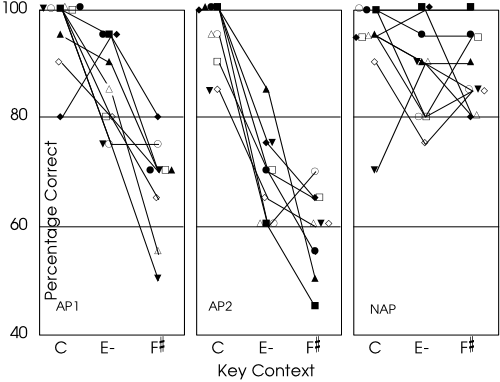
Figure 15 Percentage correct responses of individual listeners of different absolute pitch levels in the three different key contexts.
次に各調性条件における個人別の正答率をFigure 15に示す。AP1群では、ほとんどの被験者が、C majorできわめて正確な判断をしているのに対して、E- major, F# majorとなるにつれて判断が著しく不正確になっていることがわかる。特にF# majorの調性条件ではチャンスレベル程度の正答率しか示していない被験者が少なくない。これに比べて非絶対音感 (NAP) 群の被験者では、調性条件の間での正答率の違いはそれほど顕著ではない。
反応時間
メロデイーが提示されてから被験者が反応するまでに要する時間は、被験者が判断をするために行っている内的処理過程をうかがい知るのに有用な情報となる。この実験では、比較メロディーの最後の音が鳴った時点から被験者が反応キーを押すまでの時間を反応時間として測定した。しかし、たとえば第2音が変化音である場合には、被験者は違いがわかれば、メロディーが終わるまで待つことなく反応するので、反応時間はマイナスの値になることもある。一方same試行では、比較メロディーの第4音まで聞かなければ同異の判断をすることはできない。従って反応時間の絶対値はここでは意味がなく、調性条件間の違いだけに着目する。
Figure 14の折れ線グラフに、被験者グループ別に、各調性における反応時間の平均を示す。絶対音感群はどちらも同一調条件にくらべて移調条件で反応時間が長くなっているのに対して、非絶対音感群はどの調性条件でもほぼ同じ程度の反応時間の値を示している。絶対音感レベルの要因を被験者間要因とし、調性条件を被験者内要因とする2要因分散分析の結果、絶対音感レベルの効果は有意ではなかった [F(2, 24) =0.96]。一方、調性の効果は有意で [F(2, 48) =32.05, p<.001]、絶対音感レベル×調性の交互作用も有意だった [F(4, 48) =4.11, p<.01]。交互作用は、同一調条件では絶対音感群の方が非絶対音感群よりも反応時間が短いのに対して、移調条件ではそれが逆転して絶対音感群の方が反応に時間がかかるようになっていることを反映している。
絶対音感レベルと調性の間の交互作用が有意であったので、各被験者グループ別に1要因分散分析を行って、調性条件の効果を調べた。その結果、AP1群とAP2群のどちらにおいても、調性の効果が有意であった [それぞれ F(2, 16) =19.49, p<.001; F(2, 16) =10.99, p<.001]。また3つの調性条件の平均値の間の対比は、C major条件とE- major条件の間が1%水準で有意であり、E- major条件とF# major条件の間には有意な違いはなかった。これに対して非絶対音感群では調性の効果は有意には達しなかった [F(2, 16) =3.09, .1>p>.05]。この結果から、絶対音感群では、同一調条件にくらべて移調条件が反応に時間がかかり、移調条件の中でもE- majorよりもF# majorの方がさらに時間がかかると言える。一方、非絶対音感群の反応時間はどの調性条件でも有意な差はない。
個人別に反応時間の傾向を見るために、各被験者群別に各調性条件の反応時間を個人ごとに示したのがFigure 16である。AP1群とAP2群ではほとんどの被験者が、同一調条件にくらべて移調条件で反応時間が長くなる傾向を示している。これに対して非絶対音感群では、絶対音感群の被験者に見られたような傾向はあまり顕著には見られない。各個人別に全試行の反応時間について調性条件を要因とする分散分析を行った結果、調性の効果が有意になったのは、絶対音感群では18人中16人であったのに対して、非絶対音感群ではひとりもいなかった。
〈考察〉
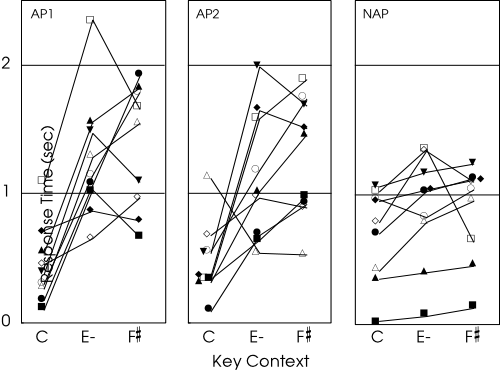
Figure 16 Average response times of individual listeners of different absolute pitch levels in the three different key contexts.
この実験で得られた結果から、絶対音感保有者は相対音高を知覚すべき課題においても、絶対音感を用いる傾向があり、それが有効に機能しないときには、遂行成績の著しい低下や反応の遅れを生じる場合があるということが結論される。これはこれまでに報告した調性コンテクストの中での音程知覚の実験の結論 (Miyazaki, 1993, 1995) と一致するものである。絶対音感を持つ人々と持たない人々とでは、音程やメロディー、和声などを処理し知覚するやり方が違っている場合があると考えられる。そのようなストラテジの違いから、遂行成績や反応時間の違いが生じると言えよう。
C majorの調性で比較メロディーが提示される場合、楽譜に表記されているのと違った高さの音が鳴ったら違うという反応をすればよいわけであるから、AP群の被験者は絶対音感を用いることによってきわめて正確にかつ素早く反応することができたと考えられる。事実C majorでのAP群の正答率は96%ときわめて高いレベルに達している。NAP群の正答率はこれにくらべるとかなり低く87%でしかない。この違いは、少なくともこの調性条件のもとでは、相対音感を用いて判断するやり方に比べて、絶対音感を用いるやり方がきわめて効果的であることを示している。ただし、AP群とNAP群の音楽的レベルが必ずしも等しくなかったという可能性は指摘しておかなければならない。この実験では、音楽経験に関してある程度の幅がある被験者を、絶対音感テストの成績によって、AP群とNAP群に振り分けた。絶対音感は幼児期の音楽訓練を通じて学習されるものであるので、音楽経験のレベルを等しくするという特別の配慮をしない限り、AP群の方がNAP群よりも全体の音楽経験のレベルは必然的に高くなってしまう。従ってAP群とNAP群の正答率の違いの一部はこのようなもともとの被験者グルーブ間の音楽的レベルの違いによるものかもしれない。
しかしたとえそのような音楽的レベルの違いがあったとしても、E- majorとF# majorにおいては、AP群の成績は逆転してNAP群よりも悪くなっている。この結果は、そうした被験者グループ間の音楽的レベルの違いを打ち消して、絶対音高と相対音高というストラテジの違いの効果が強く現れたものと解釈することができる。すなわち、AP群の被験者は楽譜とは異なる高さでメロディーが鳴ったときには、相対音高ストラテジに乗り換えることができず、絶対音高ストラテジを固守し続けようとする傾向がある。このストラテジは、楽譜通りの高さでメロディーが出される場合以外には有効に機能しないと考えられるので、ここで見られたような低い正答率になったと言える。AP群の被験者がこのように絶対音高ストラテジを固守する理由としては、標準刺激が絶対音高を示している楽譜であるということと、そもそも切り換えるべき相対音高のストラテジを十分に用いることができるように訓練されていないという両方の可能性が考えられる。
なお、AP群と同様の調性条件の効果が、わずかではあるがNAP群の正答率にも見られたことは、被験者のグループ分けが不完全で、NAP群に振り分けられた被験者の中にも部分的な絶対音感を持つ被験者が混じっていたことによるものと考えられる。特にCの音だけは比較的正確にわかるという部分的絶対音感はかなり多く見られるものであり、そのような場合にはC majorで鳴り響くメロディーの認知が促進されることがあると予想される。
AP群の被験者が、楽譜とは異なる高さでメロディーが鳴り響く場合に、著しい遂行成績の低下を示す場合があるということが確認されたが、メロディーの調性によって遂行成績に違いがあるだろうか。E- majorの方がF# majorよりも正答率が有意に高かったことから見て、メロディー全体が標準的な音高基準 (たとえばA4 = 440Hz) からずれていることそれ自体は、遂行を阻害するものではないということが言える。少なくとも今回の実験の結果から見る限りでは、遂行成績に影響する要因のひとつは、楽譜からの直線的な音高距離であると考えられる。最も正答率が低かったF# majorは、C majorから主音が直線的音高距離の点で遠く離れているが、E- majorはそれよりもC majorに近い。しかしF# majorは調性の5度圏上でも最も遠い調であるので、調性的な距離が関係している可能性もある。ただ楽譜とは異なる高さでメロディーが現れた場合にAP群の被験者が用いた絶対音高ストラテジは、表象された楽譜の絶対音高と聞こえてきた音の絶対音高との音階上 (あるいは場合によっては鍵盤上) のステップ数を数えるというものであり、楽譜から表象されるメロディーを心の中で移調した上で、聞こえてきたメロディーと比較するというものではないので、直線的な音高距離の要因の方が強く影響していると考えることができるだろう。
以上考察してきたのと同様のことが、反応時間の結果からも言える。AP群の反応時間がC majorの場合だけとび抜けて短いのは、この場合だけ絶対音高ストラテジが有効に機能したことを示すもうひとつの証拠である。このことはまた、絶対音高処理は、それが有効に機能する場合には相対音高処理よりも時間がかからない直接的な処理であることを物語っている。楽譜とは異なる高さでメロディーが提示される、E- majorとF# majorの条件では、AP群の被験者は絶対音高ストラテジを固守して、聞こえてきた音と楽譜に記された音との音程関係を頭の中で計算するといった複雑な処理をしていたために、反応時間が長くなったと考えられる。結果的にはそのような処理に要する時間は、NAP群の相対音高ストラテジとそれほど違わないものになっているが、AP群の正答率が、E- majorとF# majorの条件ではNAP群よりも低くなっているということを考えると、これらの条件では絶対音高ストラテジが有効には機能しなかったと言うことができる。
この実験におけるような、楽譜とは異なる高さで聞こえてくるメロディーを知覚するという実験課題は、実際の音楽の場面では普通にはない状況である。したがってこのような条件のもとでメロディーの比較判断の成績が悪かったからといってそれは絶対音感の問題点を示すものではないという議論があるかもしれない。それどころか、音楽的には普通の状況である楽譜通りの高さで現れるメロディーの場合には、遂行成績はAP群の方がNAP群よりも良かったのであるから、この実験結果はむしろ絶対音感の音楽的利点を示すものであるとも言える。従来、素朴に絶対音感が音楽的に望ましいものと主張されてきたのは、実はそのような論拠からであった。もちろん絶対音感には、音楽的活動を営む上で役に立つ面があることは否定できない。たとえば相対音感では音をとるのがきわめて難しいようなパッセージでも、楽譜からそれを表象することができたり、耳で聞いて即座に楽譜に書き留めたりすることなどは、絶対音感の利点としてしばしば言われることである。しかし絶対音感の利点は、確かに音楽家にとってはこの上もなく便利なものかもしれないが、それは音楽的には必ずしも本質的な意味を持つものではない。絶対音感は両刃の剣であり、その利点は裏返すと音楽的に不利な結果を生じるものとなる。絶対音感の利点が音楽的には比較的皮相なことに関わるものであったのに対して、絶対音感の不利な点、すなわち相対音高や調性に関する不利は、音楽の本質にかかわるものであるということに注意すべきである。そしてこの不利が不利として絶対音感保有者に感じられることがないような状況こそが問題なのではないだろうか。
3.3 実験3
絶対音感は、そのほとんどが3-5歳頃から音楽教室などでピアノのレッスンを中心とする音楽訓練の中で獲得されたものと考えられる。現代の日本では、こどもに対する早期の音楽訓練が非常に広く行われていることから、絶対音感を持つ者の割合が非常に高い。一般には、絶対音感は音楽的資質の一つと見なされ、そのために絶対音感の訓練を目的とする音楽教室が多く存在する。ところがこれまでの研究、および前の2つの実験の結果では、絶対音感保有者は音程の認知や移調されたメロディの再認に困難を感じる場合があることが示された。そこでこのような傾向が、日本以外の絶対音感保有者にも見られるのかどうかを検討するために、ポーランドのワルシャワにあるショパン音楽アカデミーの音楽専攻学生を被験者にして、移調されたメロディの再認の実験を行った。
〈方法〉
実験課題は実験2と同じで、視覚的に提示される標準メロディと聴覚的に提示される比較メロディが同じか違うかを判断することが被験者の課題である。
刺激 提示されるメロディはすべて等しい長さの7音からできていて、調性的と非調性的の2種類がある。調性的メロディは全音階音だけからできており、すべてドレミで読むことができる。非調性的メロディは音階外音をいくつか含んでいて調性がはっきりしないメロディで、ドレミだけでは読むことはできない。

Figure 17. Examples of the tonal standard melodies visually presented in notation (a) and the corresponding comparison memodies presented auditorily (b).
聴覚的に提示される比較メロディは、楽譜の標準メロディと同じ高さか (一致条件: Cコンテクスト)、または楽譜とは異なる高さに移調されて提示される (不一致条件)。移調される高さは、楽譜よりも4半音低いA-flatコンテクスト、または6半音高いF#コンテクストである。Figure 17に標準メロディと比較メロディの例を示す。Figure 17 (a) は視覚的に楽譜として提示される調性的な標準メロディの例で、常にC majorの調性で記譜され、Cの音から始まる。Figure 17 (b) は、その標準メロディと対にして聴覚的に提示される比較メロディの例で、3通りの音高コンテクスト条件ごとに、標準メロディと同じ場合と異なる場合の例をそれぞれ示した。○で囲まれている音符が変化音である。比較メロディの前に調性を確立する2つの和音 (V7−I) のカデンツが提示され、それによって被験者には比較メロディの調性 (音高コンテクスト) があらかじめわかるようになっている。比較メロディは、常にその前に出されるカデンツで示唆される調の主音から始まり、その調性は毎試行予測できない順序で変化する。比較メロディと標準メロディとが同じ場合は、音高コンテクスト一致条件では標準メロディとまったく同じ繰り返しであり、音高コンテクスト不一致条件では標準メロディを異なる高さに正確に移調したものになる。また比較メロディが標準メロディと異なる場合は、最初と最後の音を除いた5音のうちのどれか1つの音が、音階の1ステップだけ上または下に変化している。ただしメロディの輪郭 (ピッチの変化方向のパターン) が変化することはないようにした。メロディに先行する和音ひとつの持続時間は640 ms、そのあと和音一つ分の休止をはさんで比較メロディが提示される。比較メロディの1音あたりの持続時間は320 msecである。
調性的メロディと非調性的メロディをそれぞれ60種類作成し、3つの音高コンテクスト条件にそれぞれ20ずつを割り当てた。メロディの作成にあたり、各コンテクスト条件のメロディセットの複雑さができるだけ同等になるようにするために、メロディの音高が変化する回数 (旋律輪郭の屈曲点) が条件間で同じになるようにした (音高が変化する回数が1回のメロディ数が2、2回が6、3回が6、4回が4、5回が2)。またメロディの中の隣り合う音の間の音程は1半音から1オクターブまでの範囲に及び、一つのメロディの中の音程の平均も2.17〜6.33半音の範囲であるが、各音高コンテクスト条件の中での平均は3.32〜3.66半音におさまるようにした。さらに各音高コンテクスト条件の20のメロディ対のうち、同じものが8対、異なるものが12対あるが、異なる対の12のうち、変化音が1半音変化する場合は4対、2半音変化する場合は8対ある。変化音のメロディ内の位置も、コンテクスト条件の間でほぼ均等になるように配慮した。
装置 刺激メロディーの発生、被験者の反応の取り込み、反応時間の計測は、ノート型コンピュータ (Apple, Macintosh PowerBook 170) とそれに接続したMIDIインタフェース (Apple) によるMIDIシステムを用いて行われた。標準メロディはコンピュータの液晶モニタの中央に提示され、刺激音はシンセサイザ音源 (Roland SC-88) のピアノ音で、ヘッドフォンから適度な大きさで提示された。実験のプログラムはHyperCardと、それに内蔵されたプログラム言語であるHyperTalkによって記述された。被験者の反応装置としては、MIDIシステムに接続された音楽用鍵盤 (Korg) を用いた。
手続き 被験者はコンピュータのモニタとその手前におかれた反応用の鍵盤に向かってすわる。まずコンピュータのモニタの中央に標準メロディが楽譜の形で視覚的に提示される。その3秒後に、調性を確立するための2つの和音 (V7 −I) から成るカデンツが聴覚的に提示され、すぐそれに続いて比較メロディが聞こえてくる。被験者の課題は、楽譜の形で視覚的に提示された標準メロディと聞こえてきた比較メロディとの絶対音高の違いは無視して (比較メロディがどの高さで現れても)、両者が相対音高の点で同じか違うかを、キーボードの指定された反応キーを押すことによって答えることである。キーボードの中央の6個のキーに、左から順にD3, D2, D1, S1, S2, S3というラベルが貼られていて、 被験者は、比較メロディーが標準メロディーと違うと判断した場合にはD (different) で始まる3つのキーのうちのどれかを、同じと判断した場合にはS (same) で始まる3つのキーのうちのどれかを、できるだけ速く押す。数字の大小は判断の確信度を表しており、従って配列の外側のキーほど確信を持って同じまたは違うという反応をする場合に押すキーである。また比較メロディが標準メロディと違うことがわかったら、比較メロディーが鳴り終わるまで待つことなく、できるだけ速く反応するようにと指示した。標準メロディーの楽譜は、被験者が反応キーを押すまで、モニターに提示されたままになっている。
被験者が反応をすると、そのたびに反応の正誤と反応時間がフィードバックされる。モニターのResponse Historyと書かれた領域の中に、反応が正反応の場合には○印が、誤反応の場合には●印が書き加えられていく。被験者にはここにできるだけ○をたくさん並べるように言った。これによって、被験者はこの実験に一種のゲーム感覚で取り組むことになり、実験に対する動機づけを高めることができたと考えられる。反応終了後、もう一度鍵盤のどれかのキーを押すと、その1秒後に次の試行の楽譜が提示される。このように被験者は試行系列を自分のペースで進めていくことができる。
調性/非調性条件 (2)×音高コンテクスト条件 (3)×繰り返し (20) の120試行で1ブロックとし、各被験者は2つの試行ブロックを別々の日に行った。従って各被験者は、全部で240試行を行ったことになる。ブロック内では調性/非調性の条件はランダムな順序で現れ、音高コンテクスト条件は試行ごとに予測できない順序で変化した。また2つのブロックは試行の順序が異なっている。
被験者 被験者はワルシャワのショパン音楽アカデミーのソルフェージュのクラス、および音響工学のクラスを受講している学生26人である。5オクターブの範囲の60音を用いた絶対音感テストを同時に行って、その結果から絶対音感群 (正答率 55%−100%) 9人と非絶対音感群 (正答率45%未満) 17人に分けた。全員が音楽専攻の学生であるが、幼児期 (3−6歳) から音楽の訓練を開始したものは7人だけで、また絶対音感保有者の割合も日本の音楽大学生にくらべて少ない。
〈結果〉
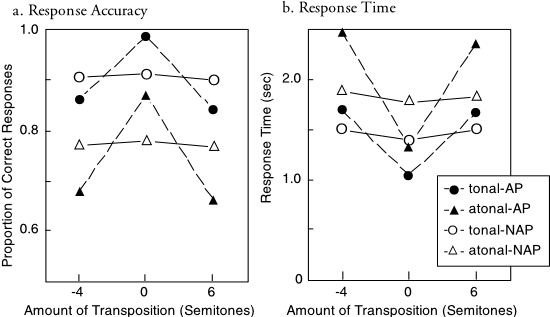
Figure 18. Summary of melody recognition test.
Figure 18a は、異なる音高コンテクスト条件のメロディ再認課題における正答率の平均を被験者群別に示したものである。横軸の移調量 (音高コンテクスト) が0の場合が、楽譜と聞こえてくるメロディが同じ高さレベルである一致条件であり、移調量が-4と6の場合が、楽譜とメロディの高さレベルが一致しない不一致条件である。
正答率データに関して、絶対音感レベルを被験者間要因、音高コンテクストと調性を被験者内要因とする3要因分散分析を行った。その結果、絶対音感レベルの主効果は有意ではないが [F(1, 24)=0.27]、音高コンテクストの主効果 [F(2, 48)=30.37, p<.001] と絶対音感レベル×音高コンテクストの交互作用 [F(2, 48)=25.54, p<.001] が有意であった。これは、絶対音感群の正答率は、一致条件ではきわめて高く、不一致条件ではかなり低いのに対して、絶対音感を持たない被験者群の正答率はすべての音高コンテクスト条件でほとんど同じレベルであることを示している。このような傾向は、調性条件と非調性条件のどちらでも同じ程度に見られる。これは絶対音感レベル×音高コンテクスト×調性の交互作用が有意でないことによって裏付けられる [F(2, 48)=2.21, p>.1]。
調性の主効果 [F(1, 24)=164.65, p<.001] は有意であるが、絶対音感レベル×調性の交互作用は有意ではない [F(1, 24)=0.47]。これは調性/非調性条件の間の違いが、絶対音感群と非絶対音感群で同じように見られることを示している。非調性条件ではメロディを調性の枠組みの中でとらえることができないため調性条件にくらべて判断が難しいので、正答率はどちらのグループでもほぼ一様に低くなっている。
絶対音感レベル×音高コンテクストの交互作用が有意だったので、絶対音感群と非絶対音感のそれぞれの正答率について調性と音高コンテクストを被験者内要因とする2要因分散分析を行った。絶対音感群の分析では、調性の主効果 [F(1, 8)=65.49, p<.001]、音高コンテクストの主効果 [F(1, 24)=28.39, p<.001] がともに有意で、両者の交互作用は有意ではなかった。すなわち絶対音感群では、一致条件にくらべて不一致条件の遂行成績が低いという音高コンテクストの効果が、調性条件と非調性条件のどちらでも同じように見られると言える。3つの音高コンテクスト条件の間の対比を見ると、一致条件不一致条件 (CとA-flat、CとF#) の間の差は有意であるが、A-flatとF#の不一致条件同士の間の差は有意ではなかった。一方、非絶対音感群の分析の結果、調性の主効果 [F(1, 8)=110.19, p<.001] のみが有意で、音高コンテクストの主効果 [F(1, 8)=0.77]、および両要因の交互作用 [F(1, 8)=0.95] は有意ではなかった。すなわち非絶対音感群の遂行成績は、調性条件にくらべて非調性条件の方が低いが、どちらの場合も音高コンテクスト条件の間で違いはないと言える。
一致条件についてだけ見ると、絶対音感レベルの効果が調性条件 [F(1, 24)=7.43, p<.02] と非調性条件 [F(1, 24)=5.48, p<.03] のどちらにおいても有意になった。これは、一致条件では絶対音感群の方が非絶対音感群を上回っていることを示している。一方、不一致条件についてだけ見ると、絶対音感レベルの効果は調性条件 [F(1, 24)=2.02, p>.1] では有意でないが、非調性条件 [F(1, 24)=4.93, p<.05] では有意だった。すなわち、不一致条件における遂行成績は、調性条件では絶対音感群と非絶対音感群に有意な違いはないが、非調性条件では絶対音感群の方が非絶対音感群よりも遂行成績が低いと言える。
反応時間の結果 (Figure 19b) は、正答率のパターンとちょうど裏返しである。非絶対音感群では、どのコンテクスト条件でも反応時間にほとんど違いがないが、絶対音感群では、一致条件にくらべて不一致条件の方が反応時間が長くなっていることがわかる。
反応時間データに関して、絶対音感レベルを被験者間要因、音高コンテクストと調性を被験者内要因とする3要因分散分析を行った。その結果、絶対音感レベルの主効果は有意ではないが [F(1, 24)=0.01]、音高コンテクストの主効果 [F(2, 48)=19.48, p<.001] と絶対音感レベル×音高コンテクストの交互作用 [F(2, 48)=12.96, p<.001] が有意であった。これは、絶対音感群の反応は、一致条件ではきわめて速いが、不一致条件ではかなり遅くなっているのに対して、絶対音感を持たない被験者群では反応時間がすべての音高コンテクスト条件でほとんど同じくらいであることを示している。また絶対音感レベル×音高コンテクスト×調性の交互作用も有意になった [F(2, 48)=5.86, p<.01]。これは一致条件にくらべて不一致条件の反応時間が長いという絶対音感群に特有の傾向が、調性条件よりも非調性条件で一層顕著に見られることを示している。
調性の主効果 [F(1, 24)=23.5, p<.001] は有意であるが、絶対音感レベル×調性の交互作用は有意ではない [F(1, 24)=0.28]。これは調性/非調性条件の間の違いが、絶対音感群と非絶対音感群で同じように見られることを示している。調性条件にくらべて非調性条件では判断が難しいので、反応時間はどちらのグループでもほぼ一様に長くなったと考えられる。
絶対音感レベル×音高コンテクストの交互作用が有意だったので、絶対音感群と非絶対音感のそれぞれの反応時間データについて調性と音高コンテクストを被験者内要因とする2要因分散分析を行った。絶対音感群の分析では、調性の主効果 [F(1, 8)=22.03, p<.002]、音高コンテクストの主効果 [F(1, 24)=10.40, p<.002]、両者の交互作用 [F(2, 16)=5.14, p<.02]がすべて有意であった。すなわち絶対音感群では、一致条件にくらべて不一致条件の方が反応が遅いという音高コンテクストの効果が、調性条件よりも非調性条件で顕著に見られると言える。3つの音高コンテクスト条件の間の対比を見ると、一致条件と不一致条件の間の差、すなわちCとA-flat [F(1, 8)=16.85, p<.001] ならびにCとF# [F(1, 8)=14.22, p<.002] の間の差は有意であるが、A-flatとF#の不一致条件同士の間の差は有意ではなかった [F(1, 8)=0.11]。一方、非絶対音感群の分析の結果は、調性の主効果 [F(1, 8)=10.77, p<.005] のみが有意で、音高コンテクストの主効果 [F(1, 8)=2.14, p>.1]、および両要因の交互作用 [F(1, 8)=0.50] は有意ではなかった。すなわち非絶対音感群の反応時間は、調性条件にくらべて非調性条件の方が遅いが、どちらの場合も音高コンテクスト条件の間で違いはないと言える。
Figure 19a〜dは、調性条件と非調性条件のそれぞれにおける絶対音感群と非絶対音感群の正答率を個人ごとに示したものである。絶対音感群では、1人を除いて、すべての被験者が、一致条件にくらべて不一致条件で正答率の低下を示している。これに対して非絶対音感群ではほとんどの被験者で、音高コンテクスト条件の間に差はない。反応時間の結果 (Figure 20a〜d) も同様であり、非絶対音感グループでは、ほとんどの被験者がどのコンテクスト条件でもほとんど反応時間に違いはなかった。これに対して絶対音感グループでは、ほとんどの被験者が、一致条件にくらべて不一致条件で反応時間が長くなる傾向を見せた。
Figure 21は、各個人のメロディ認知実験の正答率と絶対音感テストの正答率との関係を散布図の形で各条件別に示したものである。一致条件 (Figure 21c, d) では、メロディ・テストと絶対音感テストの成績の間に正の相関が見られ、相関係数は、調性条件が r=.4537, 非調性条件が r=.4808 になった。特に非調性条件 (Figure 21c) では、絶対音感テストの成績が上位の12人についてだけ見ると強い正の相関 ( r=.8861) があり、正確な絶対音感を持つ被験者ほどメロディ再認の成績が高い傾向があると言える。このような相関は、絶対音感を持つ被験者が、楽譜と同じ高さで聞こえてくるメロディを認知するときに、絶対音感を用いていることを示す結果と解釈される。
これに対して、不一致条件 (Figure 21a, b, e, f) では、メロディ認知と絶対音感の正確さの間に負の相関が見られた。この傾向は正答率が上限に近くなっている調性条件ではあまりはっきりしないが、非調性条件では比較的明らかである。この結果は、一般に、絶対音感が正確になるにつれて、楽譜とは異なる高さに移調されたメロディの再認成績が低くなる傾向があることを示している。実際に、最も正確な絶対音感を持つ被験者は、一致条件でのメロディ再認の成績がきわめて高いが、これは相対音感、あるいは調性的なコンテクストの中でのピッチ関係についてのセンスからくるものではなく、絶対音感によるものであると言える。これらの被験者の不一致条件のメロディ再認の成績が低いことが、この見方を裏付けている。
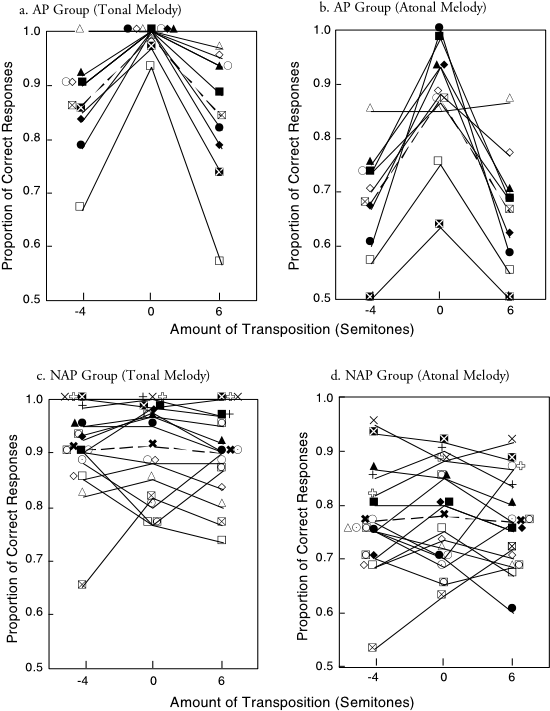
Figure 19. Individual accuracy of melody recognition test
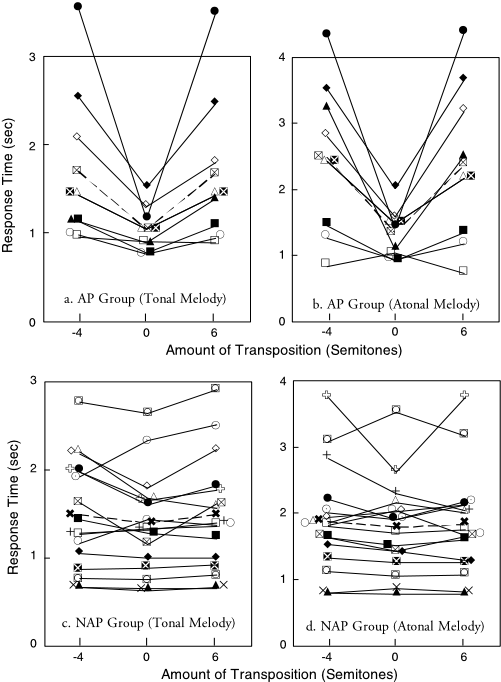
Figure 20. Individual response time of melody recognition test
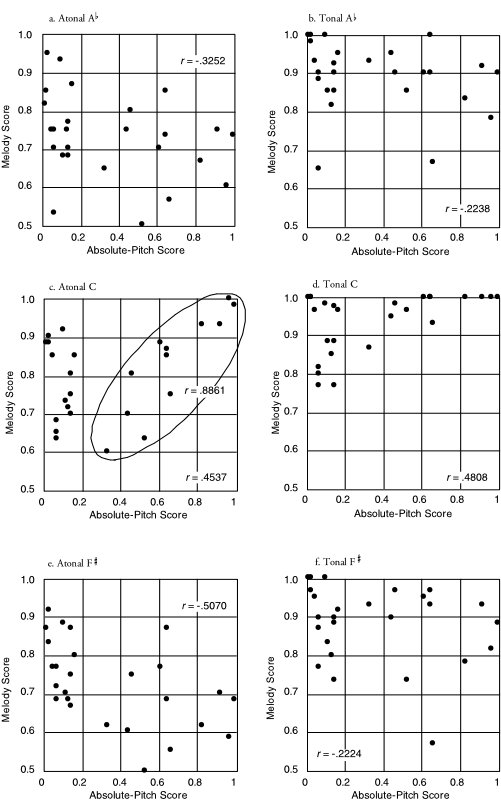
Figure 21a-f. Correlations between absolute-pitch score and melody-recognition score
〈考察〉
この実験の結果、絶対音感を持つ被験者は、聴覚的に提示された比較メロディが、楽譜の形で視覚的に提示された標準メロディとピッチが一致しないとき、メロディの再認が困難であることが明らかにされた。
伝統的な楽譜表記法は、音楽の絶対音高の情報を表すものであり、メロディは絶対音高の系列として楽譜に表記される。しかし楽譜には相対音高情報をも表されており、それこそが楽譜から読みとるべき、音楽的に重要な情報である。絶対音感を持たない人々が楽譜から読みとるのは絶対音高ではなく相対音高である。この実験で、絶対音感を持たない被験者は、どの調性条件においても、相対音高情報を用いることによって同じような正確さでメロディを判断することができた。彼らは絶対音感を持っていないので、楽譜の標準メロディと聴覚的に提示された比較メロディのピッチの違いに影響されることはなかったのである。これに対して、絶対音感を持つ被験者は、メロディ再認実験を通じて絶対音感ストラテジを用いたと考えられる。絶対音感ストラテジによって、一致条件では高い正答率を達成することができたが、不一致条件ではそれは役に立たず、正答率の低下を招くことになった。絶対音感を持つ被験者の不一致条件における低い成績は、楽譜に示されている標準メロディのピッチと、聞こえてくる比較メロディのピッチの間の不一致から来るものと思われる。もし絶対音感を持つ被験者が絶対音感を完全に抑えて相対音感に切り換えることができるならば、このような成績の低下が起こることはなかったはずである。実験の結果が示すように、実際には、ほとんどの被験者が不一致条件で成績の低下を示した。このことは絶対音感を持つ被験者が絶対音感ストラテジに固執する傾向があることを示している。
楽譜からピッチのイメージを容易に作ることができるということが、絶対音感の音楽的利点の1つであるということは言えるかもしれない。しかしここに報告した実験の結果から考えると、絶対音感保有者が持つメロディの楽譜からイメージするのは、Gestaltとしてのメロディではなく、固定した絶対音高レベルに結びついたものなのかもしれない。
4. 結論
絶対音感保有者の相対音高処理に関する実験の結果から、絶対音感保有者が、Cのコンテクスト以外の場合には相対音高を認知することが困難になる場合があることが明らかにされた。これは絶対音感を持つ人々が、相対音高を処理することを必要とするような場合にも絶対音高ストラテジに固執する強い傾向があることを反映しているものと言える。このストラテジはCのコンテクストに固定した移調不能なスキーマのようなものなのかもしれない。事実、ある被験者は、絶対音高ストラテジに固執して、楽譜や鍵盤のイメージを操作したり、指を折って数えたりといったやり方で、音程やメロディの判断をしていたと語った。このことは、絶対音感を持つ被験者が、音程やメロディを、調性的コンテクストを背景としたピッチ関係としてではなく、個別的なピッチの単なるつらなりとして聞く傾向があることを示唆している。このような聴取ストラテジは音楽的聴取からはほど遠いものである。
音楽において本質的に重要なものは調性的コンテクストの中におけるピッチ関係であるということを考えると、ピッチ関係をとらえる上でのこのような困難は、絶対音感保有者が一種の音楽的ハンディキャップをかかえているかもしれないということを示唆している。もし絶対音感を持つ音楽家の中に音楽的ハンディキャップをかかえる人々がいるということになると、これは音楽教育にとって重大な問題となる。
絶対音感保有者は、幼児期の訓練によって絶対音感を身につけたが、音楽的にはるかに重要な相対音感は完全に発達しないままになっていることがあるかもしれない。いったん正確な絶対音感を身につけると、音楽活動において、絶対音感に頼ることの方が相対音感を用いるよりもはるかに簡単だからである。その結果、絶対音感は相対音感の発達に妨害的な影響を与える場合があると考えられる。とするならば、幼児期からピアノのレッスンを始め、その結果、絶対音感を獲得した子供たちに対しては、相対音感を十分に発達させるための、慎重に計画された系統的な訓練が用意される必要があると言えるだろう。
絶対音感保有者を被験者とした音程の知覚とメロディ再認の実験結果は、絶対音感の音楽的意義について疑問を提起するとともに、さらに進んで絶対音感の好ましくない側面を示唆するものである。絶対音感は音楽的に役に立つものである場合もあるが、その反面で音楽にとって有害なものとなることもある。絶対音感が音楽的に役に立つものであるということはよく話題になるが、しかしそれは音楽的にはあまり重要なことではない。ところが絶対音感の好ましくない側面はあまり問題にされることがなかった。しかしその側面は音楽的に最も重要な側面に関するものである。従って、絶対音感を身につけた子どもたちに対しては、相対音感の発達が絶対音感によって妨げられることがないように注意をはらう必要があるだろう。さもないと、ある意味で音楽的なハンディキャップを持った音楽家が生まれてくることになるかもしれない。
References
- Bachem, A. (1950). Tone height and tone chroma as two different pitch qualities. Acta Psychologica, 7, 80-88.
- Bachem, A. (1955). Absolute pitch. Journal of the Acoustical Society of America, 27, 1180-1185.
- Brady, P. T. (1970). Fixed-scale mechanism of absolute pitch. Journal of the Acoustical Society of America, 48, 883-887.
- Burns. E. M., & Ward. W. D. (1982). Intervals, scales, and tuning. In D. Deutsch (Ed.), The psychology of music. New York: Academic Press.
- Cuddy, L. L. (1968). Practice effects in the absolute judgment of pitch. Journal of the Acoustical Society of America, 43, 1069-1076.
- Cuddy, L. L. (1968). Training the absolute identification of pitch. Perception & Psychophysics, 8, 265-269.
- Dowling, W. J. (1978). Scale and contour: Two components of a theory of memory for melodies. Psychological Review, 85, 341-354.
- Meyer, M. (1899). Is the memory of absolute pitch capable of development by training? Psychological Review, 6, 514-516.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97.
- Miyazaki, K. (1989). Absolute pitch identification: Effects of timbre and pitch region. Music Perception, 7, 1-14.
- Miyazaki, K. (1990). The speed of musical pitch identification by absolute pitch possessors. Music Perception, 8, 177-188.
- Miyazaki, K. (1993). Absolute pitch as an inability: Identification of musical intervals in a tonal context. Music Perception, 11, 55-72.
- Miyazaki, K. (1995). Perception of relative pitch with different references: Some absolute-pitch listeners canユt tell musical interval names. Perception & Psychophysics, 57, 962-970.
- Moore, B.C.J. (1982). An intoroduction to psychology of hearing. London: Academic Press.
- Pollack, I. (1952). The information of elementary auditory displays. Journal of the Acoustical Society of America, 24, 745-749.
- Revesz, G. (1913). Zur Grundlegung der Tonpsychologie. Leipzig: Veit.
- Sergeant, D. & Roche, S. (1973). Perceptual shifts in the auditory information processing of young children. Psychology of Music, 1, 39-48
- Shepard, R.N. (1964). Circularity in judgments of relative pitch. Journal of the Acoustical Society of America, 36, 2346-2353.
- Shuter-Dyson, R., & Gabriel, C. (1981). The psychology of musical ability (2nd ed.). London: Methuen
- Stumpf, C. (1883). Tonpsychologie I. Leipzig: Hirzel
- Takeuchi, A. H., & Hulse, S.H. (1991). Absolute-pitch judgments of black- and white-key pitches. Music Perception, 9, 27-46.
- Wedell, C.H. (1934). The nature of the absolute judgment of pitch. Journal of Experimental Psychology, 17, 485-503.
- Wellek, A. (1963). Musikpsychologie und Musikaethetik: Grundriss der systematischen Musikwissenschaft. Frankfurt: Akademischer Verlag.
Back