トピックス
『移動する地域社会学―自治・共生・アクターネットワーク理論』刊行のお知らせ
掲載日:2024年05月20日
伊藤嘉高著『移動する地域社会学―自治・共生・アクターネットワーク理論』が、人文学部の研究叢書として知泉書館より刊行されました。本書は、筆者が20年間にわたって日本国内外の地域社会で行ってきたフィールドワークの成果を、アクターネットワーク理論(ANT)を基軸に据えて世に問うものです。
ANT は「社会学者が外から勝手に説明しないための理論」です。あらゆる存在は(主体であれ客体であれ、言説であれ法則であれ)他の存在との連関(結びつき)によって形づくられており、そうした連関から新たな存在や新たな連関が絶えず生まれていくと考えます。そして、調査対象である出来事を形づくっている連関を新たに発見していこうとする方法がANTです。
少し考えてみれば、わたしたちの個々の行動は、経済や社会の構造に規定されたり、本来的に主体的であったりするのではなく、その時々の他者や理念、物事と の結びつきによって形成されていることが分かります。ANTはこの直観をどこまでも大切にしており、結びつきを超えた存在を外部から持ち込むことを禁じます。
本書では、医療や福祉、観光や防災などを媒介にして、人びとがどのように結びつき、行動を変容させ、人びとが共生する単位である地域社会がどのように組み直されていくのかを描き出しています。その上で、地域社会のありようを外から批判して満足するのではなく、実地に根ざした多様な存在の連関による地域社会の絶えざる組み直しに貢献しようとする営みとして「移動する地域社会学」 を位置づけています。
本書執筆のモチベーションを与えてくれたのは、学部のゼミ生たちと大学院生たちでした。ANT とその周辺をめ ぐる難解な議論に辛抱強く付き合ってくれたことに感謝しています。実際に、本書のアイデアのいくつかはゼミでの議論を通して 生まれたものです。今年度のゼミでは、これまでの地域社会の組み直しのなかで不可視化されてきた「ケア」をめぐる調査研究を学生たちとともに行っていきます。
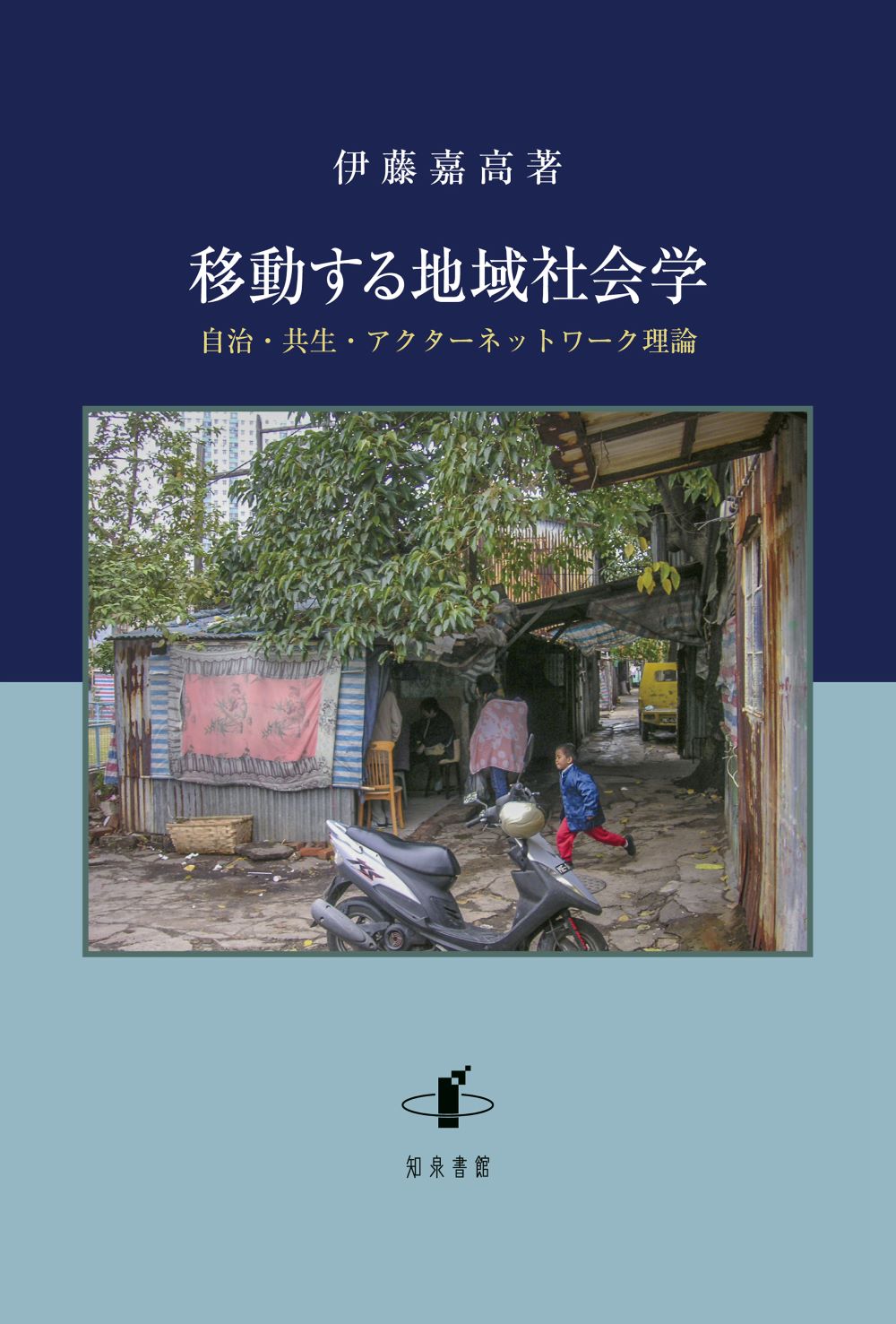
(記/伊藤嘉高)
(『学部だより』31号より一部加筆修正)



